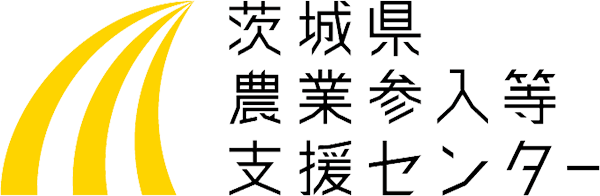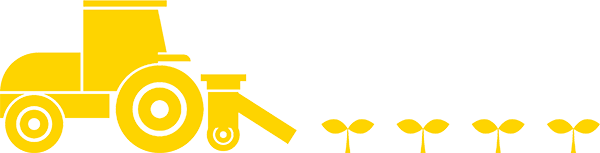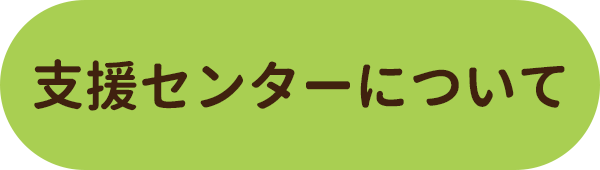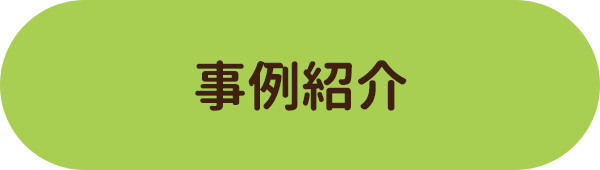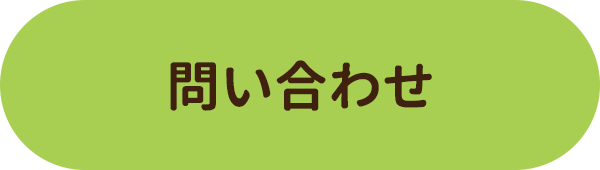おみ農園

おみ農園
地域:鉾田市
支援内容:法人化、事業計画の策定
主品目:かんしょ、ミニトマト
経営面積:約11ha
手作業にこだわった“干し芋”を届けたい
おみ農園は、現在の経営の中心である小見陽介さんの祖父の代から続く農家で、父・洋市さん、母・秀代さんとの家族3人で農業を営んでいます。かつてはメロンを中心に栽培し、2010年頃から「かんしょ(さつまいも)」栽培へと転換。現在、生産したかんしょの約4割を「干し芋」として自家加工して直売所やECサイトで直接販売を行い、残りの約6割を卸売業者や食品加工会社などに卸しています。干し芋づくりは父の洋市さんが始め、原料となるかんしょの生産から加工までこだわりを持って、じっくり時間をかけ丁寧に作られる高品質な干し芋は、近所の人から“おいしい”と評判になり、次第にテレビやインターネット上でも取り上げられて話題となり、いまや多くのリピーターがいる人気商品となっています。
専門家のアドバイスで、家業の継承と拡大を考慮した法人化計画へ
「家族3人で仕事を回してきましたが、両親も会社員であれば定年となる年齢となり、自分が家業を継承する段階に差し掛かってきたことに加え、ありがたいことに年々伸び続けている需要に対して、こちらの供給が追いつかなくなりつつあることが、法人化を決意させました」と陽介さんは語ります。さらなる干し芋販売の拡大、安定した農作物栽培体制の構築などを考え、おみ農園を法人化することを目指し、茨城県農業参入等支援センターの専門家派遣を利用することにしました。
法人化に向けて中小企業診断士、税理士、社会保険労務士、司法書士らの専門家派遣が行われ、経営課題の整理や手続きについてアドバイスを受けました。「専門家の方々から、それぞれの視点から法人設立にあたって詳しく説明していただけたのは貴重な経験でした」。特に印象に残っているという複数回の派遣を受けた中小企業診断士からの支援では、はじめの経営診断において「運営基盤は整っているものの、今後の規模拡大を踏まえると経営の方向性を明らかにすることが必要」という結果だったため、5年後を目標年とした事業計画書を策定しました。陽介さんは「中小企業診断士さんから法人化の骨組みとして、相続や継承をスムーズに行えるような仕組みを提案してもらえたのが大きかったですね」と、派遣時に受けたアドバイスを活かしながら現在法人化への手続きを進めているそうです。
農業をイチから学んだからこそ、新たな挑戦ができる!
陽介さんが実家のおみ農園に就農したのは2021年。高校卒業後に知見を広めるべく大学では経営学を専攻すると、食品業界の最先端である食品卸業者に就職し営業職として多数の商品を取り扱った後、茨城県立農業大学校へ通い、農業をイチから学びました。
「高校卒業が間近に迫った2011年3月11日に東日本大震災が起きました。その時に両親が避難所で干し芋などを提供している姿を見て農家が地域で果たす役割の大きさを実感しました。そんな中で、この仕事を両親の代で終わらせたくない、この地域を盛り上げたいという気持ちも芽生えたのが、現在の出発点かもしれません」。震災をきっかけに兆した地元農業への想いと就農前に大学で学んだ知識や社会人としての経験を農園運営に活かしながら、「最近は他品目の農園を訪れて栽培方法を学びながら、新たな作物栽培の可能性を探っています。また、良い意味で農業一本でやっていくという事にこだわっていないので、例えば加工分野なら、干し芋以外の商品開発に挑戦するのもいいかもしれないですね。そのためにも法人化だとか共に働いてくれる人材の雇用が今後は必要になってきます」とこれからの事業展開にも更なる意欲をみせます。
「ときどき販売先の売り場にお客さんの様子を見に行ったり、お客様からの感想をお聞きしたりするのですが、干し芋を“おいしい”と喜んでくれることが何よりも嬉しいですし、大きなやりがいになっています」と、購入者からの喜びの声を原動力にするおみ農園は、新たな農業経営スタイルを示しながらこれからも地元農業を牽引していくことが期待されます。

農園の中心である小見陽介さん

畑から採れたかんしょは天日干しで時間をかけながら干し芋になっていく

中身が見やすい透明のパッケージや規則正しい並べ方など細部までこだわりの詰まった干し芋