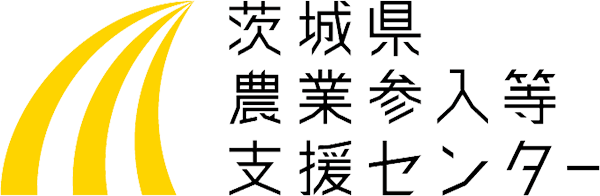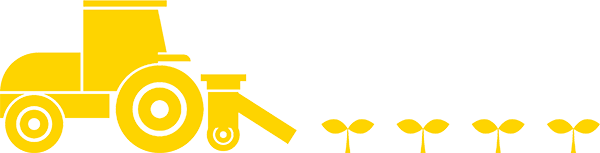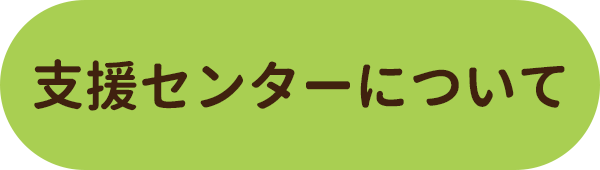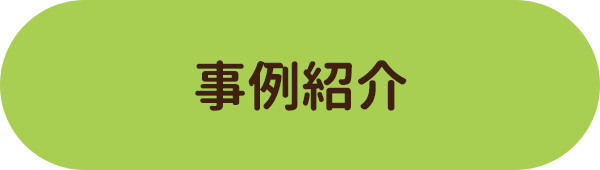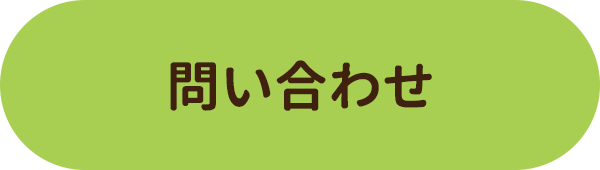鈴木 秀史

鈴木 秀史
地域:下妻市
支援内容:法人化、雇用・労務管理
主品目:水稲、小麦
経営面積:約45ha
スマート農業で挑む新しい農業経営の形
鈴木秀史さんは下妻市で水稲と小麦を生産している農家で、スマート農業を積極的に導入することで、家族と常時雇用1名の少人数経営でありながら生産規模を拡大。飼料用米の収量や生産技術を評価する「2024年度 飼料用米多収日本一」コンテストで、関東農政局長賞を受賞しました。
鈴木さんは2020年に就農した若手認定農業者で、妻・ひとみさんの父親の体調不良がきっかけで農家の後継者となりました。それまでは民間企業で営業を担当し、農業経験は年に何度か義父を手伝った程度とほとんどありませんでした。「会社員から農家に転身して、農業について何もわからない状態から始めました。そこで、効率的な方法を自分で色々と調べるうちに“スマート農業”に辿り着きました。経験や勘といったものが少なかったからこそ、これらを取り入れてみようという考えができたのだと思います」。鈴木さんのスマート農業の導入は、直進アシスト機能付きトラクターからはじまり、無人ロボット田植機、農業用ドローンなど、多岐にわたり作業の効率化に取り組んでいます。「いまはインターネットの動画サイトでも情報が得られますので、情報収集が毎日の日課となっています。農業機械を扱う販売会社でもまだ手探りの部分も多く、機械によっては私が初の導入事例になるなど一緒になって試行錯誤をしている状態です」と、鈴木さんの積極的な姿勢はスマート農業の業界全体にも寄与しています。
支援センターのアドバイスで経営の“見える化”を行い、規模拡大と法人化へ
スマート農業技術の導入による作業の効率化もあり、就農当初20haだった耕作面積は大幅に拡大していたため、新たな働き手の確保や法人化を検討していました。「私は会社員でしたので、従業員を雇うにあたり社会保険への加入を考える必要があることはわかっていましたが、調べてみると手続きが複雑でした。そこで支援を受けるために農業参入等支援センターに相談しました」と語る鈴木さん。
中小企業診断士からの支援では、収入と支出のバランスを“見える化”して、今後の機械投資などへの計画的なコスト管理のために現時点の財務状況を確認しました。また、雇用・労務管理について人材育成3ヵ年計画の策定を行い、社会保険労務士から社会保険や労働保険加入手続きの説明やアドバイスを受けました。「これまで農作業への比重が大きかったのでどうしても事務作業が疎かになっていましたが、“見える化”していただいたおかげで、規模の拡大やその先の法人化に向けてそれまで何となく考えていたことに関して『こうやっていけばいいんだ』と気づけたことが多くてよかったです。人材の育成計画も口頭で教えるだけとは違い、計画書があることで社員教育がやりやすいかもしれませんね」と支援センターのアドバイスが役立ったことを話します。これらの支援を経て、かねてからの知人を2025年の1月より従業員として雇用し、今後の規模拡大に向けて共に農作業に励んでいます。
誰もが作業ができる環境を構築して効率的な経営を目指す
現在、鈴木さんは、衛星画像と人工知能を活用した栽培管理システムで、稲の生育状況や収穫時期などをスマートフォンなどの情報端末で管理できる環境を整備しています。データを蓄積することで情報の精度も高まり、さらには農業用機械が作業をアシストしてくれるので、鈴木さん自身が栽培現場まで行かずとも、経験や専門知識が少ない従業員に作業を委ねることが比較的容易になっています。今後、農地の規模を拡大していくうえでカギになる、従業員それぞれがデータに基づき効率よく作業できる現場の環境が整いつつあり、さらには経営面での土台も数年後の法人化により固めていこうとしているところです。「法人化は経営的な課題解決でもありますが、いずれ次の世代に引き継ぐことを考えたものでもあります」と語る鈴木さん。未来を見据えて常に情報にアンテナを張り、効率的な手法を取り入れ続ける新時代の農業経営体として、さらなる成長が期待されています。

代表の鈴木秀史さん

栽培管理システムを活用し、離れた場所からでも、ほ場の状況把握が可能に

農業用ドローンも作業の効率化には欠かせないツールの一つ